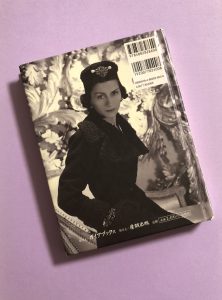『VOGUE ON ココ・シャネル』ブロンウィン・コスグレーヴ、鈴木宏子翻訳(ガイアブックス、2013年)
書名の通り、「VOGUE誌に掲載されたココ・シャネルの物語」である。VOGUE誌はハイファッションの最先端を行く雑誌のひとつ、掲載商品の貸し出し元にも欧州の名門ファッションブランドが軒並み名を連ねる。世界各国で出版されている。日本ではVOGUE JAPANと称し、毎月発売されている。1892年より発行されており、ココ・シャネルの活躍した2000年代がそのままVOGUE誌に取り上げられていることになる。
そのVOGUE誌に掲載されたココ・シャネルのデザインスケッチ、写真、またココ・シャネル自身のポートフォリオとともに、彼女の言葉を紡ぎながら物語が書かれている。
スキャンダルの極めて多いココ・シャネルに関しての伝記は多く、彼女自身も取材に対して心地よく応じていた。それはややもするとスターとしてのココ・シャネルが過剰に描かれており、ファッションデザイナーココ・シャネルを見失いがちである。本書はVOGUEの名を冠しているようにファッションデザイナーとしての魅力に忠実である。VOGUE誌がココ・シャネルによってその売上を大きく伸ばした事実に基づいて、ココ・シャネルもまたVOGUE誌によって大きく知名度を上げ羽ばたいていったことが想像される。
本書は書籍であるが、ファッション雑誌を楽しむように読むことができる。ココ・シャネルファンでなくとも20世紀のファッション文化に興味のある人たちすべてに書かれたと言えるだろう。