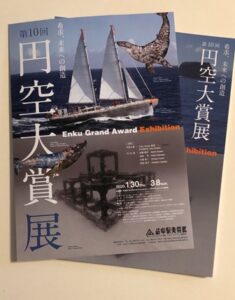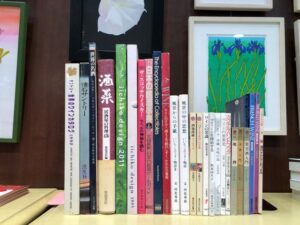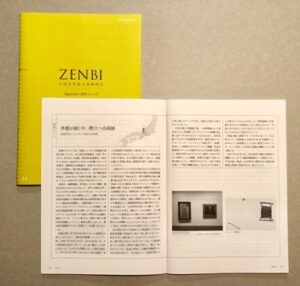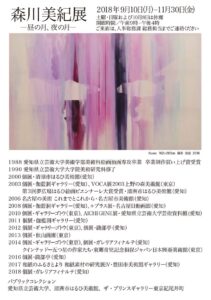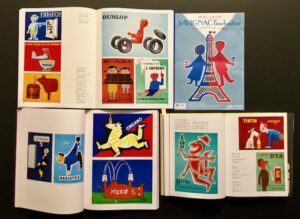愛知県芸術劇場小ホールにて、2月8日(土)に観てきた。
開演前、いきなりロビーパフォーマンス。
こういうのドキドキして期待高まる。
今から何が起ころうとしているのか。
開演後は、オーストラリア、香港、日本の6人のダンサーによる映像とのセッションパフォーマンス。
ここまで撮影フリー。
撮影でどう新たなクリエイティブで参加できるか。
ここまでくるともう観客は一気に取り込まれている、一体化。
席について、1時間。
映像とコンテンポラリーダンスによるパフォーマンスは、息もつかせぬ緊張感あふれる美しさ、力強さだった。