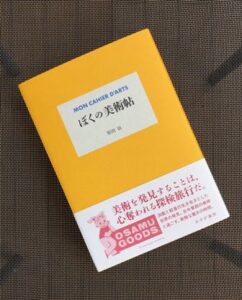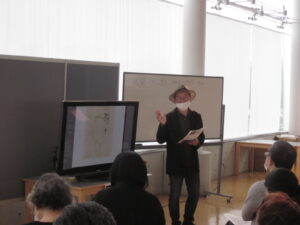『等伯』安部龍太郎(文春文庫、2015年)
アートブックシリーズで初めての小説を紹介。
もちろんフィクションですが、美術史では書けない長谷川等伯の人間模様が解ってとてもおもしろい。
もちろん実在人物なので、判っているところはすべて事実に即していると考えられる。
等伯が等伯になる前の長谷川信春(のぶはる)を克明に描いている。
そしてやはり画家の道を歩む息子の久蔵のことも。
千利休、狩野永徳、豊臣秀吉、石田三成、春屋宗園、近衛前久、歴史に連なる実在人物と等伯の関係、特に狩野派と等伯(のち長谷川派)の絵師仕事を受注する争いは、美術を美しいものとする以前に見応えのあるものである。
庶民を対象とした浮世絵とは異なり、天下人の寵愛を獲得することなしに屏風絵、襖絵は存在しない。
また残り得なかったとも言える。京の富裕商人も天下人に習って贔屓としたのである。
美術に限定するまでもなく、文化の領域で小説の主人公として取り上げられる人物がいかに少ないことかと思う。
まず知名度があって、人生にドラマがあって、主人公に関する資料がどれだけ残されているか。絵師は描いた絵が大きな資料となる。
等伯の場合も代表作《松林図》をはじめ多くの屏風絵、襖絵が残されており、そこから人生を読み取ることができる。
小説『等伯』によって、等伯の人物像を浮かび上がらせることができる。その上で《松林図》を観ることは、人間ドラマとともに楽しむ、美術のあじわい方の一つであると思う。
小説『等伯』は直木賞受賞作であるが、美術と文学に虹の橋を架けるエンターテイメントである。