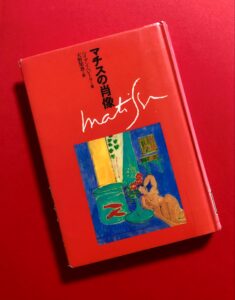『青木繁と坂本繁二郎』松本清張(新潮社、1982年)
松本清張は『或る「小倉日記」伝』で芥川賞受賞、代表作に『点と線』『眼の壁』『砂の器』『火の路』など、古代から歴史もの、現代小説、推理小説、社会派小説などその領域は極めて広く、かつ重厚な小説家である。さらに美術をテーマとしたものが何冊かあり、本著もその一冊である。
青木繁と坂本繁二郎は、ともに現在の福岡県久留米市に同年に生まれ、同じ高等小学校で学び、同じ洋画塾で画家を志し、東京美術学校(現東京藝術大学)に学んだ。青木は在学中より華々しいデビューを果たし、《海の幸》を代表として天才と称されるも晩年は貧困と病の中、九州各地を放浪し、28歳という短い生涯を終えた。一方坂本は数年遅れてデビュー、パリ留学後は、福岡へ戻り、87歳で亡くなるまで長きにわたって、馬、静物、月などを題材にこつこつと制作に励んだ。
本著は二人の関係、人生を追いながら、二人の代表的な研究者河北倫明をはじめとする多くの著述を紐解き、的確な美術評論を展開している。夏目漱石がそうであったように、小説家の美術評論は奥が深く、なお秀逸な文章力は読者を強く惹き込んでいく。破天荒で天才的な青木は、愛人福田たねを伴って壮絶な物語を描いていく。そして本著の7割を過ぎたあたりで、坂本に話が変わる。しかし坂本を主人公にしたここからが本著の真骨頂であり、推理力を含めて圧倒的におもしろい。青木の陽に対して坂本の陰は、生涯において背負った重い運命であった。坂本もまた多くの言葉を残しているが、その殆どが青木を意識したものであり、考えそのものの奥に青木の大きな存在がある。画家青木繁がいなかったとしたら画家坂本繁二郎もまた存在しなかったに違いない。
松本清張は、ほかに『天才画の女』『岸田劉生晩景』があり、美術と美術家に対する深く鋭い洞察力は、美術評論家とは異なる人間を見る力に溢れている。