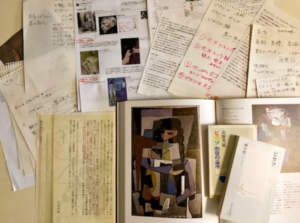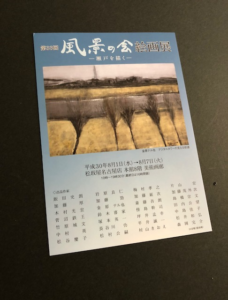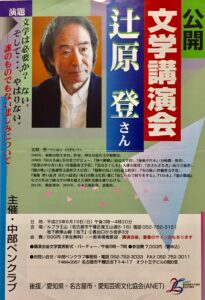岐阜池田町の極小美術館へ、現在開催中の「加藤由朗展」「南谷富貴展」を観てきました。
グラフィックデザイナーとして50年、加藤さんのコンセプトの力強さは変わらず、凄い。
デザインの大きな力はアイデア。そしてそれをヴィジュアル化するセンス。単体としては1枚のポスター、個展会場ではそれらが群れのパワーとなって迫ってくる。
木片ブロックでインスタレーションを展開している南谷さんは、今展ではひび割れた木材から採取、ブロックに委ねる形が魅力的。
「ブロックを塗装していると、ずっとピシッ ピシッって音がし続けている」という話が印象的だった。
自然からのラストメッセージを身体でキャッチしながら制作している。自然への敬意と自らの造形が美しいセッションを奏でている。
クレパスは「ももいろ」だった。なぜ「ももいろ」は使われなくなったんだろう。英語が氾濫したということもある。しかし、青い、赤い、黒い、白いなど形容詞になる基本の色は、英語化の頻度は低い。多くの色の中で、「ももいろ」の発音は重くて籠る。「ピンク」は弾ける発音で、耳障りが良い。かわいい色のNo.1とピンクの発音のかわいさが、ピッタリきている。
一方で、桃色は桃の花の色(桜色も桜の花の色)というように、具体的な色を表している。ピンクは赤と白の間の幅広い色として呼ぶことができるので、とても使い勝手が良い。幅広いピンクのイメージを限定するためには、コーラル(珊瑚)ピンク、サーモン(鮭)ピンク、チェリー(桜)ピンク、そのほかベビーピンク、ショッキングピンク、ダスティ(濁った)ピンクがある。
残念ながら、日本色名に幅広いピンクに該当するものがない。
(絵:サノエミコ)
6月18日(日)中部ペンクラブ主催による辻原登公開文学講演会が開かれ、聴講した。幅広い博学の中から「文学とは何か」「文学の責任とは何か」を語られた。講演を聴いて考えたこと。
最近の国会を見ていると、言葉の使われ方が異常に乱れている。質問と答弁が呼応していないばかりではなく、文脈が成り立っていない、言葉の使い方が間違っている、更には読めない。国会発言で読めないというのは、発言内容が自作ではないということの暴露で、そういうところからも品格の無さが露呈する。
長く美術教育の職にあったが、学生たちが絵のタイトルを「無題」ときどることが増えてきた。理由を問えば「私の想いは言葉にできるものではないから絵を描いている。題に惑わされて絵を見てほしくない」という。一見もっともらしい。しかし、そういう学生の多くは何を描きたいか追求することが甘く、題を考えることを面倒くさいと思っている。そこに都合の良い言い訳がある。
世の中の多くの人が深く考えることを避けるようになったと思う。考えるとは数式を解くときに考えるということを指すのではなく、人生のこと、社会のことについて考えることである。人間関係で悩み、苦しみ、憤る、不条理に怒り、心の悼みに寄り添う。
考えることは、人としてあるべき姿を自らに求めるものであり、そこから品格は生まれる。「無題」と題された絵は、考えませんでしたという絵があって、考えていない絵はつまらない。一方で熟考の末にある「無題」は、恐ろしい。
多くの絵は題と共に合って、一体化したものである。
ムンクの「叫び」は叫ばなくてはならない観る者への呼び醒ましがある。あの絵が「無題」であったら、こんなに多くの人の共感を得ただろうか。
毎月、文芸誌の表紙を木版画で制作している。版制作、刷り技術は上達するし、上手くなりたいと言う職人意識も常にある。15年前に木版画を始めたが、その頃の作品は今より技術は下手である。しかし、作品が良くないかというとそうではない。むしろ、木版画を始めたばかりの楽しさが版画に感じられてなかなか良い。
表現技術は、観る人を感動させることがあるが、感動させるために表現技術が磨かれるべきではない。
創作者は表現技術の上達に酔ってしまうことがある。誰もが判りやすく、「上手い!」と賞賛してくれる。これが危険。
岡本太郎は「絵は上手くっちゃいけない、下手な方がいい」と言っていますが、これの意味するところが表現技術賞賛の否定。写真が発明されコンピュータ時代にあって、表現技術賞賛は意味がない、そこに目を奪われてはいけない。
では本当に下手な方が良いのかというとそういう意味ではない。
一番大切なことは、創作者の想い。伝えたい想いのない上手い絵というのはつまらないということである。
創作者の想いを実現するために、表現技術が必要で、そのために磨かれる。それは必ずしもデッサン力があるとか超絶技巧という意味ではない。
デッサンは表現技術の骨をなすもの、ですがデッサン至上主義は主客転倒である。
想いと技術が一つになった時、美術が生まれる。